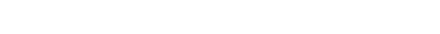この人なくして『ダンス オブ ヴァンパイア』は語れない。
畏怖と孤独、チャーミングさを感じさせるクロロック伯爵を日本初演から演じ、観客を虜にしてきた山口祐一郎さん。本作に挑む思いを伺った。
聞き手・文:宇田夏苗
舞台写真:2015年帝劇公演より
この記事は博多座会報誌「喝采」(2019年12月号)に掲載されたインタビューです。博多座様より許諾をいただき当ホームページにて転載させていただきました。(一部加筆修正している個所がございます。)
──2006年の日本初演から五演目となる今回、再びクロロック伯爵役に臨むにあたり、何か準備などはされたのでしょうか。
準備といえるかわかりませんが、ヴァンパイアの伝承が生まれた東欧を旅してきました。吸血鬼といえば、この作品の舞台でもあるルーマニアですが、そこに行ってしまうと、クロロックとしては居心地が良すぎて、おそらく日本に戻れなくなってしまうでしょうから(笑)。ハンガリーを訪れたらとても面白かったんです。前回、東欧を旅したのがEU加盟以前だったので、キャッシュレス化が進んでいたりいろいろ様変わりしている一方で、人々の暮らしの素朴さがまだ残っているのが新鮮でした。ある時、公共バスに乗ったら、どうも自分が目指しているのと違う方向に進んでいる気がするんですね。慌てて降りたら、すぐに運転手さんと乗客のひとりの若い青年が降りて来て、どうしたんだと。必死に事情を伝えたら、お二人ともが懇切丁寧に教えてくれて、世話をしてくれたこともありました。公共の温水プールでは老若男女の人たちが楽しそうに戯れていて。その様子を眺めているうちに、ふと『ダンス オブ ヴァンパイア』の世界を想像したりしました。
──旅先でもそうやって作品のことを考えられているのですね。初演の千穐楽には、当日券を求めて1,200人以上が帝国劇場に並んだことは今や伝説になっています。一度観るとハマるといわれる、『ダンス オブ ヴァンパイア』がそこまで人々を虜にするのはなぜだと思われますか。
やはり、作品の持っているパワーですよね。大きな装置で圧倒するような舞台が多い中、演出の山田和也さんをはじめスタッフの方たちがアイデアを凝らして、あえてシンプルに作ったことにより、計らずも作品の力が最大限に伝わった。僕たち俳優だけでなく、ダンサーの方一人一人にいたるまで、全員のエネルギーがお客様に届いた、芝居が生きたのだと思います。それは初日の幕が開いた後に、この作品に関わった誰もが感じたことでした。初演からこの十三年の間に大きく変わったことといえばSNSですよね。この作品は、舞台の宣伝にブログなどの手法を生かした先駆けでもあったと思います。

──欲望の解放を謳うクロロック伯爵と、人間の理性を掲げるアブロンシウス教授。“欲望”と“理性”の対決は、今の世界情勢と重なるようにも見えて、なかなか風刺的でもありますね。
風刺劇でもコメディーでも、どんな風に捉えて頂いてもいいんです。観る方によって、これほど自由に解釈できる作品は稀有だと思いますね。クロロックは、すべての欲望が解放されてこそ、永遠の命があるんだという存在。いわば欲望の解放の具象化でもあるわけですが、そういうことは説明するよりも、観た方がそれぞれに感じて頂ければいいことですから。ただ、世界を見れば国、人間同士の覇権争い、利権の奪い合いは続いていて、欲望と理性が対決しているともいえるわけです。またそういう世の中に生きていて、息苦しさを感じている方は多いのではないでしょうか。無意識であってもいつの間にか社会に、何かに縛られて、ある形にはめ込まれているような気がするというね。僕もそういう現代社会で育った人間ですが、舞台の上では欲望を解き放つ存在として、ここまでやるのか!というのを観て楽しんでいただけるようにと思って臨んでいます。

──人間社会をシニカルに描きつつ、笑いもあり、熱狂かつ怒涛のエンディングへと向かっていく『ダンス オブ ヴァンパイア』。最後にあらためて、お客様へのメッセージをお願いします。
演出家の方がよく偶然、必然ということをおっしゃるのですが、これまで舞台活動をしてきて、あの時の出会いや選択が、ここにつながったのかと思うことがあります。その時に、自分はこの作品を、役をやることを求められていたんだと、必然だったと実感するんですね。それは人生の喜びですよね。この作品もそんな経験をさせてくれたものの一つです。是非劇場にいらして、一瞬でも自分を解き放って本来の自分の姿になって、大いに楽しんで頂けたらと思います。